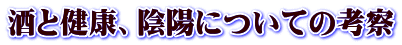 2025年7月27日 2025年7月27日 |
2回目の帯状疱疹ワクチンを接種した当日に高熱は出なかったのですが、副反応は胃と腸の絶不調となってやってきました。 1回目の接種で何も起きなかったので油断をして二日間は普通に食事をしました。 当然晩酌は欠かしません。 その三日後からは四日間スープとヨーグルトだけの生活になりましたし、やむを得ず休肝日となりました。 美味しく呑めない状況下で嗜むのはお酒への冒涜と考えています。
5日後に病院に行って副反応じゃないかと聞いてみましたが、可能性があるかもしれないとのこと様子見となり胃薬が処方されました。 国の施策なので医者もはっきりさせてはいけないのでしょうね!! 10日以上過ぎた今は普通食に戻りましたし酒も解禁です。 酒抜きの食事は満足感が決定的に欠けます。 改めてというか実に久し振りに分かりました。 まあ今更ですが!
そのような味気ない期間を過ごしたことをきっかけに、酒を末永く呑み続けるために健康面から酒について考えてみてはと思いました。 これまでは世界の酒の紹介をしてきましたが、ご興味があればお付き合いください。 多少の参考にはなるかと思います。
私が自己弁護として使ってきた「酒は百薬の長」は古代中国の漢書(食貨志下)からの言葉で、“酒は適量を飲めば健康に良く、どんな良薬よりも効果のある薬である”という意味で用いられていますが、実はこの言葉、酒を国の専売制にし税収を増やそうとした中国王朝「新」の創建者である王莽が国民の理解を求めるために用いたと言われています。 遥か昔1世紀に書かれた言葉が現代まで続き使われているのは素晴らしいことです。
同じ漢書の中に「酒は天の美禄」という言葉もあって、人民を養い、宗教行事も、衰え病んだ体を養うのも酒であるとしていますが、税収を増やそうとしたことがきっかけでは言葉も色褪せます。
鎌倉時代末期には、「酒は百薬の長といへども、万の病は酒よりこそ起れ」と吉田兼好が徒然草
の中で語った警告の言葉もあります。 又、気違い水、狂水、狂薬ともいわれていました。
いずれにしろ酒は“美味しく適量”を嗜みたいものです。
その適量って? 厚労省の指標で純アルコール一日20g程度とされ、日本酒で一合、ビールで500mlのロング缶1本、ワインでグラス2杯程度、ウイスキーならダブル1杯程度です。
小柄な女性は、男性よりも肝臓の体積が小さいので、男性の2/3量(13~14g程度/缶ビール350ml)が適量とされています。
アルコールグラム数は、アルコール含有量(%)×量(ml)×0.8(比重)で計算し、アルコール含有量5%のビール500mlで20gになります。 最近はストロング系のアルコール濃度の高い飲料もあり、9%の缶酎ハイ500mlでは36gとなり、同じ500mlでもビールの1.8倍のアルコール量になります。 同じ量でより早く酔ってしまうのは健全な呑み方とは言えません。
メーカーも考えを改めて貰いたいものです。 “週に2日は休肝日をもうけることが大切です。”
酒は適量なら健康に良いといわれますが、少量の飲酒でも「頭頸部がん」のリスクがあるとの近年の報告があります。 このがんは鼻、口、のどなど顔から首の範囲の顔面から頸部まで発生した悪性腫瘍をいいます。 酒を大量に呑む人の口腔・咽頭がんのリスクは、呑まない人の“5倍”で、がんの最も大きな要因は大量で長期間の飲酒ですが、“適度な飲酒”でも発がんリスクが上昇する可能性があるとのこと、アルコールの種類(日本酒、ビール、ワイン、スピリッツ・蒸留酒)を問わず全てが危険だということです。
臓器としての肝臓からみると、一日3合(アルコール60g)呑む人を常習飲酒家、5合以上呑む人を大酒家と呼んでいます。 呑み続けると、脂肪肝、アルコール性肝炎、肝線維症、肝硬変、肝がんになる危険性が高く飲酒量が少ないほど死亡リスクが少なくなります。 私は純米酒を一日一合以下の“適度な飲酒”で適量を下回りますので、危険度も低くまあ健全な飲酒家の一人です。
アルコールは体内に入ると主に胃や小腸から吸収され肝臓で分解されます。 肝臓は人体内の大きな臓器で“巨大な超高機能の化学工場”といえます。 そこには2種類のアルコール分解酵素があり、“ADH1”(1型アルコール脱水素酵素)と“ALDH2”(2型アルデヒド脱水素酵素)です。 その役割で“ADH1”は肝臓に送られたアルコールを有害なアセトアルデヒド(吐き気や動悸、二日酔いなどの原因)に分解する酵素で、“ALDH2”はこのアセトアルデヒドをさらに分解し、無害な酢酸に変える役割を持っています。 分解された酢酸は血液によって全身を巡り、最終的に水と二酸化炭素に分解されて体外へ排出されます。
「酒に弱い」人は“ALDH2”のはたらきが弱いか“ALDH2”を持っていません。 日本人の44%ほどは“ALDH2”のはたらきが弱いか“ALDH2”を持っていないため、酒に弱かったりまったく飲めなかったりする体質です。
又、 “ALDH2”が活性するかどうかは遺伝子によって決まり、酒に強いか弱いも生まれつきの体質によって決まります。 “ALDH2”のはたらきが弱い(持っていない)人は、アセトアルデヒドが体内に蓄積しやすいため、ごく少量の飲酒でも気分が悪くなったり眠くなったりします。
“ALDH2”には、活性の高いNN型、活性が低いND型、活性がほとんどないDD型があり、人種によって遺伝子型の割合が異なります。 日本人にはND型やDD型の人が比較的多く酒に弱い人が多い傾向がありますし、日本人の40%はアルコールの分解スピードが遅い“酒に弱い”体質です。 アジア系人種は総じて酒に弱いといわれています。 急性アルコール中毒にもなりやすいし無理な飲酒は禁物です。
そして次は酒の陰陽(温冷効果)についてです。日本人には東洋医学的な見解が体に合うと考え酒と食べ物の陰陽について調べました。陰陽という言葉の持つ妖しい響きが好きなこともありますね。
☆ 先ずは酒についての誤解その ① です。
“酒は体を温めてくれるもの”との誤解を持つ方が多いように感じます。 酒を呑めば即効的に顔が赤くなったり体が温かくなります。 特に燗酒それも熱燗を呑めばさらに体が温まる感覚があります。 血管が拡がり血の巡りが良くなることで体は温まりますのでそういうことから広く世間一般的に“酒は体を温めるもの”との誤解が生じると考えます。
その体が温まる原理は体に入ったエチルアルコールが高カロリーなので、素早く燃えることで起ります。 速く燃えるものは燃え尽きるのも速く、燃え尽きた後は体細胞が失う熱量も大きく、結果飲む前よりも体が冷えるということになります。 高アルコール度の蒸留酒で顕著にあらわれます。 大酒で酩酊し寒い冬の深夜に路傍や植込みで寝込み朝方の寒さの中で凍死をしていたという話がありますし、私事では少し呑み過ぎて酔いが醒めてきた時の体が震える寒さを経験したことがあります。 酒が体を温める効果は長続きしませんし、時間が経てばかえって体を冷やすことになります。 なぜかといえば酒は“陰性”の飲み物だからです。
“酒類全般=世界中のアルコール飲料はすべてが陰性”です。 その中にも強弱がありますので、
大雑把ですが陰陽表を作りました。
食物の陰陽(温冷効果)は色々な健康番組にも取り上げられています。 一例で「秋茄子は嫁に食わすな」は、身籠った大事な嫁の体を冷やして具合が悪くならないようにと古くから言い伝えられてきました。 ナスやトマトはかなり陰性が強いので避け、陽性の根菜類を多く摂りなさいということのようです。 科学の力もないころに経験則で良い結果を導き出して広めてきた先人の知恵には感心するしかありません。
世界中で酒は食事の友ですから食べ物と酒の相性について、食べ物についても陰陽の観点からお伝えしたいことは有りますが説明も長くなりますので割愛します。
世界の酒を見ますと寒い国でも蒸留酒(陰性が強い)が飲まれています。 例としてロシアではウォッカが飲まれていますし、中国でも北方の寒い地域では白酒が飲まれています。 陰陽の視点から見るとより体を冷やす蒸留酒が消費されることは健康上問題大ありですが、あまりに寒いので一瞬の快楽を求めて飲んでしまうとのことのようです。
温帯の日本で生産される酒は清酒(陰性が弱い)が主流で理にかなっています。 その酒粕からカストリ焼酎を作りはしますが! 南方の九州、奄美、沖縄と暑い地方では各種材料で焼酎(蒸留酒)が作られます。 これも理にかなっているということになります。 沖縄より北海道のほうが気温が高くなる日もある現在、更に未来ではどうなることでしょう。
別の視点からで気温が高いところでは清酒の腐造が多くなり造りがしにくいこともあります。
火落ちするといいますが、火落ち(ひおち)とは日本酒の製法用語の一つで製造している日本酒が貯蔵中に白濁して腐造することをいいます。 乳酸菌の一種である火落ち菌(火落菌)によって引き起こされます。 そのため酒は温度管理がしやすく、安全で良酒を造ることができる寒造りが主流になりました。 今では温度管理のできる工場での四季醸造もありますが。
世界中の気候が変動し、酒米の栽培や酒造への影響が心配です。 科学の力で克服するしかないのでしょうか。 陰陽の根源にかかわってきます。
アルコール飲料の陰陽表 《酒類全般=アルコール飲料はすべてが陰性》
陰性(冷効果) 強 ⇐ 中庸 陽性(温効果)
| 蒸留酒 |
ブランデー/テキーラ/ジン/ 各種焼酎
白酒/ラム/ウォッカ/ウイスキー/ (黒糖・芋・麦・米・蕎麦) |
― |
| 混成酒 |
カルーア/カンパリ/
クレーム・ド・カシス/ |
― |
| 醸造酒 |
ポートワイン/ 白ワイン/赤ワイン/ ビール/ 清酒
シェリー/マディラ/ ベルモット/シードル/ 黄酒 |
強いてあげれば
玉子酒! |
※清酒の陰陽;清酒全体が陰性は弱く中庸に近くなる。 黄酒である紹興酒より陰性は弱い。 陰性の強いほうから大まかに並べれば、生酒←吟醸酒←純米酒←古酒の順です。
☆ 酒についての誤解その ② です。
“食べてから呑むと酔わない”と思っていましたがそうではないようです。 満腹のときにはアルコールの吸収が遅くなって酔いが回りにくく、アルコールの血中濃度も低くなるのではと思っていましたので、食事をしてから宴席に臨むこともありましたがそうではありませんでした。 そういえば悪酔いを防ぐといわれて牛乳や乳製品を摂ってから宴席に臨むこともありました。 最終的に水と二酸化炭素に分解されて体外へ排出され水分不足になるので、先に水分補給をしておくのは正解だったかもしれません。
食べ物と一緒になったアルコールは少しずつ吸収されるため、血液中のアルコールの濃度は長時間持続されます。 相当量を呑んでも酔わないので未だ大丈夫かなと勘違いしますが、実際には気持ち良くなったころには呑み過ぎになってしまっています。 要は呑む量の問題でしょう。
防ぐには! 酒は“しっかり食べながら呑む” “肴を食べつつチビリチビリ呑む”です。
酒好きな人は食物をとらない傾向にありますが、酒の肴は酒をおいしく呑むために必要ですし、栄養バランスを保ちながら肝臓を守ります。 肝臓のアルコール処理能力というと、体重10キロあたり1時間1グラム程度ですので「駆けつけ3杯」といって急ピッチで呑むことは厳禁、肝臓への負担を考えたら最悪です。 ゆったりとした気持ちで酒を楽しみたいものです。 しっかり食べながら呑む、これが一番理想的といえます。
その酒の肴は何が良いかというと、それはアミノ酸をたくさん含んだたんぱく質系のものです。 「大酒飲みは肝硬変になる」といわれてきましたが、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどの不足を招く粗食にあったとのこと、酒好きな人の中には、つまみをほとんど口にしない方もいらっしゃいますが、酒の肴は酒をおいしく呑むために必要なだけでなく、肝臓を守るために必要なので大いに食べることです。
先に肝臓の話がありましたが、肝臓は人体内の大きな臓器で巨大な超高機能の一大化学工場です。
その肝臓に必要なものがアミノ酸をたくさん含んだたんぱく質になります。 たんぱく質を多く含む肴に豆腐系のものがあります。 大豆製品は優秀な植物性たんぱく質なので多くとると良いのですが豆腐系だけでは少し寂しい。 まあ夏は冷や奴、冬は湯豆腐、栃尾のあぶらげも良い選択です。 丸くふくよかな酒には豆乳の味が濃い豆腐が良く合うなと個人的に思っています。
神々に奉げる酒といえば日本酒です。 奈良時代には麹菌の力で澱粉を糖に変える方法が確立されましたが、稲作が伝来した後の弥生時代は“口噛み酒”米を噛むことで口の中にあるアミラーゼにより澱粉を糖に変えそれを発酵させた酒として醸していました。 ほぼ二千年の歴史があります。 ちなみに中国の酒文化の発祥は紀元前7000年前といわれていますのでかなりの差が有ります。さすがに日本の様々な文化の源の中国です。 御神酒は今の世でもビールやワインに変わることはありえません。 お墓には故人の好きな色々な酒が供えられていますが。 八百万の神々の中には日本酒以外も試してみたいという先進的な神様もいらっしゃるかもしれません!
《 中国からの醸造法が定着せず、世界に類を見ない独自の醸造法(並行複発酵)が確立された日本酒を大切に、細く永く命の続く限り末永く楽しむことが出来ればと願っています。 》
|
|

